デアゴスティーニ・ジャパン
長年「ディアゴスティーニ」だと思いこんでいましたが「デアゴスティーニ」が正式だそうです。
デアゴスティーニといえば新聞広告によく出ている模型の材料などを購入すると毎号自宅に送る形式の雑誌の出版社です。
蒸気機関車D512
デアゴスティーニの蒸気機関車の模型です。
今は亡き義父がコツコツ作り上げたのですが、完成するまでに10万円以上費用がかかっていました。
そんな義父が大事に作った機関車を義母が「こんなに大きいの置かれたら部屋が狭くなる!」と言って息子にくれました。

義父が丁寧に仕上げた作品です。撮り鉄がいます。
汽笛の音、車輪の回転、ライトの点灯のスイッチをつけて楽しめるようになっています。

全長は88cmくらいです。車両は2つあり、後ろは炭水車です。
機関士が乗っています。

ボイラーの火室です。

車輪部分も精巧に出来ています。この部分は回転して動きを楽しめます。

D51の車輪部分
義父は手先がとても器用な人でこのような細かい部品を組み立てるのが得意でした。
他にもデアゴスティーニのジオラマの作品も息子にくれました。両作品を大事にしようと思います。
週刊鉄道模型少年時代
D51の蒸気機関車の模型と同じデアゴスティーニの模型、週刊鉄道模型少年時代です。Nゲージの富井電鉄、キハ1501形ディーゼルカーとキハ2001形ディーゼルカー 、キハ1001形ディーゼルカー(里山交通)がセットになっています。

田舎の風景「ぼくの夏休み」がテーマになっています。昭和30年代、帰省して過ごした夏の日を鉄道模型で再現し光と音の装置も組みこんだ、新しい鉄道模型マガジンと紹介されていた模型です。
Nゲージジオラマ製作マガジン『週刊鉄道模型少年時代』が創刊された時のものです。
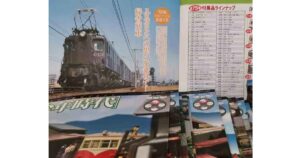
これも義父が時間をかけてコツコツと作りあげたもので、祭りの音や、夜店のライトなどリアルに再現されていて出来上がった直後に見せてもらった時は部屋の電気を消して、家族で喜んで眺めさせてもらっていました。

息子は大喜びで始終Nゲージを走らせてずっとこの少年時代の模型をじっくり見つめていました。
川の流れも再現、いかだ下りやキャンプ風景も再現しています。

村の神社と境内では夜店が並んでいてライトがつくので夜間の雰囲気も再現できます。後ろの背景も裏側は月夜の風景になっています。

踏切付近では御神輿を担いでお祭りの最中。里山駅前行きのバスが走行中。

村の神社の隣には昔懐かしい小学校があり、先生が何か生徒に話していたり、踏切向こうの里山駅ではサラリーマンの姿が。これから出勤するようです。踏切の音、電車が停車する音もリアルに再現。

この作品も義母に「置き場所に困るから持って帰ってほしい。」と言われてもらいました。細かい仕上げ部分を見てもかなりの完成度で、義父の手先の器用さに感動して今もじっくりと見てしまいます。
四隅の方まで村の人たちが仕事をしていたり、仕事の合間にみんなで休憩している場面も作成してあります。
井上陽水の歌「少年時代」や、映画「菊次郎の夏」の久石譲作曲のテーマ曲「Summer」のメロディーも流れてきそうなジオラマです。この作品も大事にしていこうと思っています。